バイク免許取得のための効率的な練習方法
「バイクの免許を取るために教習所に通おうかと思っているけれども、効率的に教習内容を習得したい!」と思っている方向けに、この記事を書いています。
こんにちは、ツーリングアプリDrivemateを運営している鎌倉です。
教習所に通うとき、「本当にバイクに乗れるようになるのだろうか?」と不安になったりしませんか?
僕もその一人で、僕の場合は知り合いの勧めもあり、普通自動二輪車の免許なしで大型自動二輪車の免許の取得に挑戦しました。スクーターにも乗ったことがない状態ですが笑。
そんな僕でも、教習を延長することなく、卒検も一発合格で大型自動二輪車の免許を取得することができました!
そこで本記事では、僕が自動車学校に通っていた期間に何をしていたかについて共有したいと思います。
「ここまでやらなくても、大型自動二輪車の免許は取得できるわ!」というツッコミもあるかと思いますが、これから大型自動二輪車の免許取得に挑戦する方々へのヒントになれば嬉しいです!
1.YoutTube動画を見まくる
2.バイク乗り降りのイメトレ
3.指導いただいた内容のメモ書き
4.車に乗っている最中のイメトレ
5.違和感を教官に伝える
6.検定コースのイメトレ
7.まとめ
1. YoutTube動画を見まくる
「YouTube動画で勉強して、お寿司を握れるようになりました!」こんな時代です笑。SNSや動画配信サイトが普及し、情報の民主化が加速する時代では、バイクの乗り方はYouTubeでも学習できます!
もちろん、バイク素人の解説動画は参考にしないほうがいいですが、自動車学校の教官が懇切丁寧にバイク運転方法を解説している動画は大変参考になりました。
僕がよく視聴していたYouTubeチャンネルは・・・
特に、ツキノワプロダクションの【月の輪自動車教習所公式チャンネル】の「教習人間バタイダーZ」シリーズの動画は秀逸です。全部見てください!
発信・停止、急制動、一本橋、スラローム、波状路、クランク、坂道・・・二輪教習に関する全ての解説動画が揃っています。
実際の教習所で学べることが動画化されているだけかもしれませんが、何度も試聴して復習できるのが動画コンテンツのいいところですね!
全ての動画が印象に残っているのですが、個人的には「急制動」が一番に参考になりました。
【すべらない急制動】急ブレーキ時のレバー握り方を徹底解説!!
「1、2、3、4、5、6、7と頭の中でカウントしながら、フロントブレーキを徐々に握っていく」というアドバイスはかなり的確で、僕自身、急制動での失敗は教えてもらった直後の初回のみでした。
YouTube動画を見るときのポイントは、「そんな乗り方もあるんだ!へぇ〜!」ぐらいの感覚で見ることです。
あからさまに「動画の内容と実際の教官の指導内容が違うじゃないか!」ということはありませんが、結局、バイク運転には「感覚」がつきものです。
感覚は人それぞれなので、動画の内容や教官の指導内容を一つひとつ試してみて、自分にしっくりくる運転を(こけながら?)探ってみてください!
2. バイク乗り降りのイメトレ
バイク乗り降りには一連の決まった流れがあります。
乗るときは・・・
「右手でフロントブレーキを握る」→「左に傾いて停車しているバイクを起こす(左に切れているハンドルを真っ直ぐにする)」→「スタンドを外す」→「右後ろを見てから跨り、リアブレーキに右足を乗せる」→「ミラーを調整する」→・・・・・
など、細かい動作がありますが、この流れをスムーズに実行します。
教習所で細かい動作を確認しながら発進するのは時間がもったいないので、この流れは家や会社の隙間時間でイメトレしておいた方が良いです。
イメトレも頭の中で想像するだけでなく、実際に体も動かして動作まできっちりと体に覚え込ませましょう!
「1日に◯◯回練習する!」と決めてイメトレしてもいいです。僕の場合は、自分の部屋を出るとき乗るイメトレ、自分の部屋に戻るとき降りるイメトレをしていました。
(習慣化が大事。第一段階が終わるぐらいまでは、ひたすら反復イメトレしてました)
3. 指導いただいた内容のメモ書き
一回一回の教習が終わった後は、自宅の部屋で注意を受けたことをA4用紙にメモ書きしました。スマホにメモるでもいいと思います!
そして、次回の教習前にはメモ書きを見て、「今日はココに注意して、教習にのぞむか」という感じで復習して、毎回の教習を受けていました。
メモ書きは財産でしかありません!
4. 車に乗っている最中のイメトレ
車に乗っている最中に、仮想バイク運転をします。特に注意していたのはギアチェンジです。
バイクと車では加速度が違いますが、車のスピードが上がってきたらギアを上げる動作(クラッチ握って、ギアチェンジ)を実際にやります。そして、停車するときも動作(クラッチ握って、ギアをローに入れる)を実際にやります。
仮想バイク運転は教習所に通う前からできます。僕の実感としては、いきなり教習所で動作を学習してやるよりも、あわてずにギアチェンジできるようになっていたと思います。いかんせん、運転に慣れないうちは、やることが多くて、心に余裕がないためです。
特に停止の動作は教習前にはある程度クセ付けできていたので、若干心に余裕を持って教習を受けられました。さすがに、ニュートラルにギアを入れる際のペダルの軽さまでは知りませんでしたが・・・笑
車での仮想バイク運転の注意事項は「ニーグリップまでは練習しない」です。
バイクに乗るときにはボディを股で強めに挟むニーグリップが重要になってきます。車での仮想バイク運転でニーグリップを意識して足のつま先を内側に絞ると(内股にすると)、右足がアクセルではなくブレーキに乗ってしまうケースがあるので注意してください。
5. 違和感を教官に伝える
「1、YoutTube動画を見まくる」でも紹介しましたが、バイク運転には「感覚」がつきものです。バイクに乗ってみて何か違和感を覚えたら、どんな些細なことでもいいので教官に伝えてみてください。運転上達のヒントをいただけると思います。
僕の場合は、スラロームで教官から大きなヒントをいただけました。
僕の場合はスラロームでハンドルを切り切れない問題が発生していました。しかも右側限定で笑。
「上体に力が入っているから、ニーグリップをしっかりして上体の力を抜く」をやってもうまくいかず。
他のコースでバイクに乗りまくって、疲れた状態でスラロームに行けばうまくいきました・・・が、これは根本的な解決になってないと僕は思っていて、「検定のときも疲れた状態になってから、スラロームに入るんですか?」という感じです。
そこで、スラロームで右にハンドルを切る際の違和感をそのまま教官に伝えました。
僕が抱いた違和感は・・・
「右側にハンドルを切るとき、なんか右手と胴体が当たって、胴体が邪魔な気がする」というものです。
そこでの教官のアドバイスが「たぶん、スロットルを強く握りすぎ。握りすぎると右腕の可動域が狭まるから」というものでした。
そして、スロットルを握る力を弱めたら、ようやく、右側にハンドルを切れるようになりました。みなさんも今、右手を力強く握った状態で右手を引く場合と、右手を開いた状態で右手を引く場合を試してみてください。右手を開いた状態で右手を引いた方が、大きく引けていると思います。
こうして僕のスラロームでの右にハンドルを切り切れない問題の原因は、「上体に力が入っているから」ではなくて、「スロットルを強く握りすぎていたから」だということがわかりました。
原因を特定、問題解決できたのは、違和感を教官に伝えたからです。みなさんもぜひ、何か違和感を感じたら教官に伝えてみてください。
6. 検定コースのイメトレ
教習も第二段階に入れば、検定コースを覚えることになります。検定コースとは、卒業検定で実際に使用されるコースです。
教習所によりますが、コースは複数存在します。僕の通っていた教習所では2つ用意されていて、卒検当日にどちらのコースで検定が行われるかを伝えられます。教習中は2つのコースを覚えて、どちらも練習します。
検定コースを覚えるためにイメトレします。僕の場合は、1日1回2つのコースをイメトレしました。実際のコースを思い浮かべて、バイクの運転をイメージします。
検定コースのイメトレには、2つのポイントがあります。
ポイント1:「3、指導いただいた内容のメモ書き」を活用する
これまでの教習で自分のつまずきポイントはメモ書きでまとめられています。そのメモ書きを意識してイメトレします。
僕の場合は「バイクのスピードにビビって、運転にメリハリがない」という問題がありました。そのため、イメトレでもバイクを「早め」にイメージします。
「ウインカーの消し忘れ」というバイクあるあるも、イメトレで結構解消されます笑。
ポイント2:ヘルメットとグローブをつけてイメトレする
実際にイメトレする際は、ヘルメットとグローブを着用すると臨場感が湧きます。卒検当日の服装でイメトレするのもGood!
イメトレでも実際の状況にいかに近づけられるかがポイントとなります。部屋の中でヘルメットとグローブの着用はちょっと恥ずかしかったですが笑。
(さすがに外でイメトレはできませんでした。不審者に見られちゃいますね笑)
7. まとめ
上記1〜6の方法を駆使して、大型自動二輪車免許の取得にたどり着けました。自宅でも教習所でも、教習期間中はバイクの運転練習に集中して、サクッと無理なく卒検に合格したいところです。
ぜひ、本記事の練習方法を参考にしてみてください。

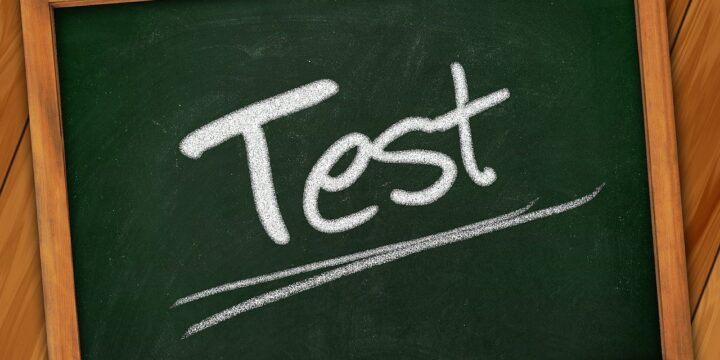

この記事へのコメントはありません。